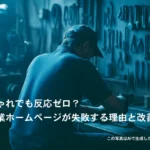トンマナの重要性と実現方法(=ブランドガイドライン)
ChatGPTもよく使う、あの言葉から
最近、Web制作やコンテンツ作成の現場で「トンマナ」という言葉を本当によく見かけます。
会話型のAIであるChatGPTも「トンマナはどうですか?」といった提案をしてくるほど、一般化してきました。
ところで、この「トンマナ」という言葉は、実は日本独自の略語(和製カタカナ語)です。
日本では略語文化が根付いていますよね。
例えば、誰もが知るハンバーガーチェーン。関東では「マック」と呼びますが、大阪では「マクド」が一般的です。
コンビニエンスストアの「セブン-イレブン」も、関東では「セブン」ですが、関西の一部では「セブイレ」と略されます。
同じブランドでも、地域によって「言い方(ルール)」が違います。
トンマナとは「流儀・作法」のこと
このように、表現には「流儀・作法」が必要です。
このビジネスにおける「流儀・作法」がトンマナ、つまり「トーン&マナー(tone and manner)」の略語です。
トーン(Tone): 色調や雰囲気。
例: 高級感を出すなら落ち着いた配色、親しみやすさを出すなら明るい配色。
マナー(Manner): 作法や様式。
例: フォントの選び方、文章の語尾(です/ます、だ/である)、記号の使い方(全角・半角の使い分け)など。
このトンマナは、ホームページ制作やSNS投稿など、あらゆる顧客との接点(タッチポイント)において、ブランドの印象を統一し、信頼感を与えるために非常に重要です。
トンマナは「感覚」ではなく「ルール」に
しかし、この「トンマナ」を「なんとなく」の感覚や、担当者個人のスキルに頼ってしまうと、必ず表現のブレが生じます。
- Aさんがつくった資料と、BさんがつくったWebサイトで、使う色が違う。
- 昨日のSNS投稿と、今日の投稿で、語尾や絵文字の使い方が違う。
こうした「ブレ」が、気づかないうちに顧客に「この会社はプロじゃないかも」という違和感を与えてしまいます。
そこで、エッグデザインオフィスとして一番おすすめしたいのが、「ブランドガイドライン」の作成です。
ブランドガイドラインとは、「うちの会社(ブランド)のトンマナはこれだ!」と明確に定義し、ルール化したものです。
ブランドガイドラインというと、以下のような大規模なものを想像し、難しそうに感じるかもしれません。
- 社名、ロゴの理由(なぜこの社名、このロゴなのか?)
- コーポレートメッセージ、コーポレートカラー
- Web制作時に使うカラーパレット、フォント(明朝、ゴシックの使い分け)
- 積極的に使うワード、NGカラーやNGワード
しかし、安心してください。完璧に完成させる必要はありません。このガイドラインをまずは作成し、必要に応じて内容をつけ足していくことで、今まで苦労していた「トンマナの共有」がほぼ解決します。これができると、誰もがブレることなく、勝手に「トンマナ」が完成します。そして、あなたの仕事が劇的に「楽」になります。
なぜ「ブランドガイドライン」が仕事を劇的に『楽』にするのか?
導入で少し触れた「仕事が楽になる」というメリット。これは単に「綺麗になる」という話ではありません。ブランドガイドラインは、あなたの企業が持つすべての課題を解決する「最強のチートシート」になるからです。
メリット1:時間とコストを劇的に削減できる
制作物のトンマナを「感覚」に頼っていると、毎回以下のような「無駄な時間」が発生します。
- 「このデザイン、前回のチラシと少し雰囲気が違くない?」という修正のやり取り。
- 「どの色にしようかな?」「このフォントでいいかな?」と毎回ゼロから悩む時間。
- 制作会社に発注する際に、イメージを言語化できないために何度も打ち合わせを重ねる時間。
ガイドラインがあれば、これらの悩みがすべて消えます。「ルール通りに進めるだけ」になるため、意思決定のスピードが上がり、制作時間が短縮されます。また、制作会社への指示も明確になるため、無駄な外注コストの削減にも直結します。
メリット2:「クライアント接点全て」で信頼感を積み重ねる
ブランドガイドラインは、単なるWebサイトやパンフレットのためだけのものではありません。
- WEBサイト制作
- チラシ、パンフレット
- 名刺
- メールの署名、営業資料
企業がクライアントと接する「全てのタッチポイント」において、統一されたトンマナが適用されます。この一貫性こそが、プロフェッショナルな企業イメージを生み出し、圧倒的な信頼感の獲得につながります。「この会社は細かい部分までしっかりしている」と感じてもらえれば、それはブランドの大きな力になります。
メリット3:ブランドを「資産」として守り、育てる
あなたのロゴやデザイン、メッセージは「うちの会社らしさ」が詰まった大切な資産です。ガイドラインは、この資産を保護する役割も担います。
実は、当社のクライアントにもこのような事例がありました。 元々、イメージに合うフリー素材のイラストロゴを使っていらっしゃいましたが、「ブランドガイドライン」を作成するにあたり、「他の企業も使えるロゴでは、うちのブランドを育てられない」と考え、当社スタッフがオリジナルのロゴを制作する提案をしました。もちろん、「色、雰囲気」といったトンマナをしっかりと合わせて。
そして、そのロゴは完成後すぐに商標登録をしました。
ガイドラインを通じて「独自ルール」を決めることは、「唯一無二のブランド資産」を確立し、商標登録などによって知的財産として守る第一歩になります。
メリット4:チームの教育コストと属人性を解消
「トンマナ」が明確でない場合、新しい担当者が入るたびに教育(OJT)に多大な時間がかかります。また、個人のセンスや解釈によって、制作物の品質がブレる「属人性※」の問題も発生します。
※「属人性(ぞくじんせい)」とは、
簡単にいえば、業務が特定の個人に依存し、その人がいなければ、遂行できない状態のこと
ガイドラインは、「うちの会社の表現ルールブック」です。新しいメンバーはこれを読めばすぐにブランドのトーン&マナーを理解できます。既存のメンバーも共通の基準で制作を進められるため、コミュニケーションのブレがなくなり、チーム全体の制作・発信力を底上げします。
中小企業こそ必要な「ブランド戦略」とは?
ブランディングと聞くと、「大企業がやるもの」「多額の広告費が必要」というイメージを持たれがちです。
しかし実際はその逆で、中小企業こそブランド戦略が大きな武器になります。
理由はシンプル。
中小企業は資金力や知名度では大手に勝てないからこそ、
“選ばれる理由”をはっきり言語化する必要があるからです。
ブランド戦略といっても難しい話ではありません。
- 誰に届けたいのか(ターゲット)
- 何で選ばれたいのか(強み・提供価値)
- どんな印象で覚えられたいのか(イメージ)
この3つが明確であれば十分です。
そして、この“軸”が決まると、トンマナやガイドラインに迷いがなくなります。
中小企業がめざすべきブランド戦略は、
1000人の「いいね」より、100人の「最高!」です。
“最高”と言ってくれたお客さまは、単なる購入者ではなく、ファンになります。
ファンはリピートしてくれるだけでなく、家族や友人、同僚に自然とおすすめしてくれる。
口コミというより、小さな営業担当のように、ブランドを広めてくれる存在です。
そしてファンが生まれる背景には、
デザイン・言葉・サービス体験が「一貫している」ことがあります。
- SNSの投稿
- Webサイトのコピー
- 店舗での接客
- 営業資料や名刺
これらすべてが、同じ価値観・同じ温度で揃っている企業は強い。
人は同じ“らしさ”を何度も体験することで、その企業を信頼し、覚えます。
つまり、
ブランド戦略=“選ばれる理由”の設計
ガイドライン=それを形にする実務ツール
この2つがそろうと、中小企業の発信は迷わなくなり、届けたい人に届きやすくなります。

ガイドライン作成は「暗黙のルール」の明文化から
ブランドガイドライン作成において、最も重要なスタート地点は、「難しそうな項目」を考えることではありません。それは、今まで社内で阿吽(あうん)の呼吸で通っていた「暗黙のルール」を、スタッフ全員で意見を出し合い、一つ残らず「明文化」することです。
なぜ「暗黙のルール」の明文化が最重要なのか?
現場には、「当たり前のことだからみんな知ってるだろ」「いちいちそんなこと言わなくてもわかるだろ」といった、言語化されない慣習や前提が大量に存在しています。
しかし、これこそがブレの原因です。
- 「うちの会社では、お客様を『〇〇様』と呼ぶのが暗黙のルールだった…」
- 「資料の行間は、なんとなく『1.5』にするのが慣習だった…」
- 「あの色は、縁起が悪いから使っちゃいけない『暗黙のNGカラー』だった…」
当事者にとっては「常識」でも、新しく入ったスタッフや外部のパートナーには全く伝わりません。その結果、「なぜか雰囲気が違う」「やり直しが発生する」といった非効率が生まれます。
暗黙のルールを明文化するメリット
この「暗黙のルール」をすべて洗い出し、ガイドラインに記載することで、以下の効果が得られます。
- 全員が同じスタートラインに立てる:スタッフ全員が「これがうちの会社の共通言語だ」と認識でき、制作物に対するフィードバックや修正のやり取りが激減します。
- 迷いがゼロになる:「いちいち聞かなくてもわかる」状態になり、作業効率が大幅に向上します。
- スタッフみんなが幸せになれる「なんでこれを知らないんだ」というストレスがなくなり、気持ちよく仕事に取り組めるようになります。
とりかかりのおすすめ
まずは、以下のテーマでスタッフみんなで会議を開き、「今まで言語化してこなかったこと」をすべて箇条書きにしてみてください。
- お客さまへの言葉遣い(例:敬語のトーン、メールの締めの言葉)
- 資料作成の基本フォーマット(例:パワポのテンプレート、箇条書きのルール)
- 社内で使ってはいけない「内輪の言葉」
- 「なんとなく」避けている色やデザイン
この「暗黙のルール」をガイドラインに記載することこそが、あなたの仕事が劇的に『楽』になるための、最も簡単で確実な第一歩となります。
ブランドガイドラインの具体的なつくり方
ここでは、難しく考えずに、まずは「箇条書き」で良いので、自社のルールを明確にするための項目と、その作成のポイントを提案します。
| ステップ | テーマ | 記事で強調したいポイント |
| ステップ1 | 「なぜ」を明確にする | ロゴや社名の理由、コーポレートメッセージ、ブランドの「核」を言語化する。「誰に(ターゲット)」、「どうなってほしいか(ミッション)」を明確にする。 |
| ステップ2 | デザインのルールを決める | 「視覚的なトンマナ」を定義する。ロゴ、カラーパレット、フォント(明朝/ゴシックの使い分け)など、具体的な数値を指定する。 |
| ステップ3 | 言葉遣いのルールを決める | 「文章のトンマナ」を定義する。語尾のスタイル、一人称の呼び方、積極的に使うポジティブワード、NGワードを指定する。 |
| ステップ4 | NG例もセットで作成する | 「良い例」だけでなく「悪い例」もセットで記載することで、ルールがより明確になり、実務で迷いがなくなる。 |
難しくない!ブランドガイドラインに「まず含めるべき」4つの基本項目
ブランドガイドライン作成の目的は、「迷いをなくす」ことです。「完璧」を目指す必要はありません。まずは以下の4つの基本項目から、自社のルールを「箇条書き」で定義していきましょう。
1. 「なぜ?」を言語化する:ブランドの核を定義する
デザインや言葉のルールを作る前に、「私たちのブランドは何者で、どこを目指しているのか」という核の部分を明確にします。これが、全てのトンマナの土台になります。
- 社名、ロゴの理由:なぜこの社名なのか?このロゴマークの形や色には、どんな意味が込められているのか?
- コーポレートメッセージ/ミッション:私たちは誰に、どんな価値を提供したいのか?(例:「すべての人の生活を豊かにする」「顧客の未来を創造する」など)
- ターゲット:誰に向けて発信しているのか?(例:30代〜40代のIT企業の経営者、子育て中の主婦層など)
POINT: この「核」が決まれば、「高級感のあるトンマナにしよう」や「親しみやすい言葉遣いにしよう」といった方向性が自然と決まります。
2. デザインのルール:視覚的なトンマナを定義する
Webサイト、チラシ、パンフレットなど、目に触れる全てで一貫性を持たせるための視覚的なルールです。
| 項目 | 定義すべき内容 |
| コーポレートカラー | メインカラー(ロゴの色)、サブカラー、アクセントカラー。必ず「カラーコード(#RRGGBB)」で指定し、使用比率も決める。 |
| フォント | 見出しに使うフォント、本文に使うフォントをそれぞれ指定。明朝体とゴシック体の使い分けのルールも決めておく。 |
| ロゴの使用規定 | 最小サイズ、ロゴの周りに設ける余白(アイソレーションエリア)、使用を避ける背景色、変形・色変更の禁止などを明記する。 |
| 画像/イラストのトーン | 使用する写真の雰囲気(例:明るい、プロフェッショナル、自然体など)や、イラストのタッチ(例:手書き風、シンプル、デフォルメなど)を指定する。 |
3. 言葉遣いのルール:文章のトンマナを定義する
読者とのコミュニケーションの「雰囲気」を統一するためのルールです。特に、WebサイトやSNSでブレやすい部分です。
| 項目 | 定義すべき内容 |
| 語尾のスタイル | 基本は「です・ます調」か「だ・である調」かを統一する。 |
| 一人称・二人称 | 会社の一人称(例:「当社」「弊社」)と読者の呼び方(例:「お客様」「お客さま」「あなた」)を統一する。 |
| 積極的/NGワード | 積極的に使いたい言葉(例:「共感」「信頼」「未来」)や、絶対に避けるべきNGワード(例:不確実な表現、他社批判など)のリストを作成する。 |
| 記号・句読点 | 句読点(、。)の使用方法、全角・半角の使い分け(例:数字やアルファベットは半角など)のルールを定める。 |
3+. 句読点について
句読点(、。)は、厳密な正解があるものではありません。
特に句読点の「、」は、位置が変わるだけで文章の意味が変わることがあります。
以下に、その違いが分かりやすい例文を3つ紹介します。
- 例1)
担当者は焦って、修正依頼を送ってきたデザイナーを注意した。
担当者は、焦って修正依頼を送ってきたデザイナーを注意した。 - 例2)
社長は驚いて、報告に来た社員に確認した。
社長は、驚いて報告に来た社員に確認した。 - 例3)
私は不安になって、連絡をしてきた相手に質問した。
私は、不安になって連絡をしてきた相手に質問した。
このように、読点の位置ひとつで、文章の解釈は大きく変わります。
誤解を生まないためには、文の意味が最も伝わる位置に句読点を置くことが重要です。
4. 迷いをなくす:NG例(してはいけないこと)をセットで載せる
ルールだけでは、実務で「これはOKなの?」と迷うことがよくあります。そこで、ガイドラインには「してはいけないこと(NG例)」を必ずセットで記載しましょう。
- ロゴのNG例 「色を変えたロゴ」「引き延ばして縦横比が崩れたロゴ」
- フォントのNG例 「本文に指定外の装飾フォントを使った例」
- 言葉遣いのNG例 「過度にフランクな表現を使った例」
【まとめ】トンマナ、ブランドガイドライン
このように、ブランドガイドラインは、一気に完璧を目指すのではなく、まずは「トンマナのブレを防ぐための最低限のルールブック」として作成し、日々の活動で疑問点が出たら随時追加・更新していくイメージで取り組んでみてください。
この記事は参考になりましたか?
この記事に関連した記事もご覧ください!
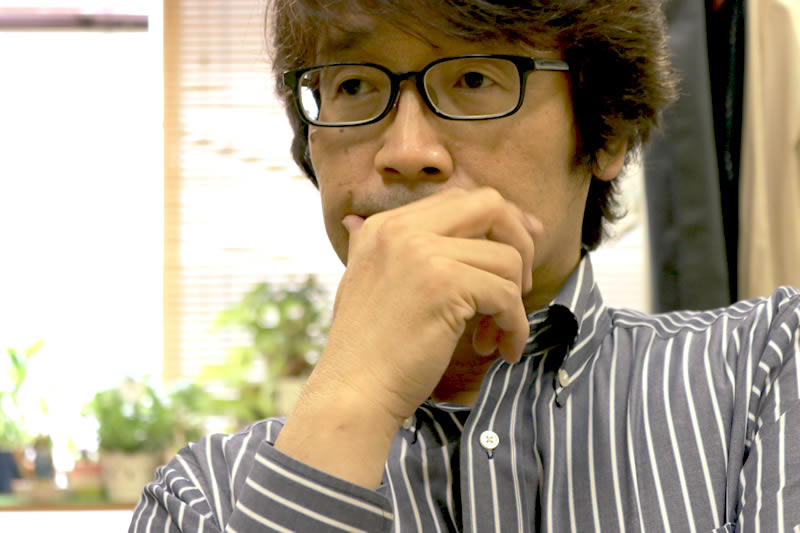
2008年1月に起業し、2026年で18年目を迎えました。これまで一貫して「成果につながるWEBサイト」をテーマに、中小企業を中心とした幅広い業種のサイト制作・運用に携わってきました。
企画・デザイン・コーディングはもちろん、公開後の運用サポートやWEBコンサルティングまでをワンストップで提供。制作だけにとどまらず、アクセス解析や改善提案を通じて売上や集客アップといった成果につなげる支援を行っています。
近年は、AI時代の検索体験(SGE / AI Overviews)への最適化にも注力し、自社およびクライアントサイトが実際にAI概要で紹介されるようになっている経験をもとに、SEO・コンテンツ戦略を検証・発信中です。
経営者からは「信頼して任せられるパートナー」として、WEB担当者からは「更新しやすく、使いやすい」と高く評価いただいています。現場で培った知見と実績をもとに、クライアントのWEB活用を支援するとともに、その実践から得た学びをブログで発信しています。
一部の制作実績はホームページ内の「制作事例」で公開中です。


 WEB戦略・ブランディング
WEB戦略・ブランディング